歯周病の基本治療とは、全ての歯周病患者さんに必要とされる、基本的な治療のことで、“初期治療”と呼ばれることもあります。
この基本治療をおろそかにすると、他の治療法(手術など)を行ったとしても、よい治療結果・長期的に良好な状態の維持は実現出来ません。
1.歯周組織検査
まず、歯周病の程度を調べるための“歯周組織検査”を行います。
歯周組織検査では、歯周ポケット(歯肉溝)の深さ、歯ぐきの出血状況、歯垢の付着状況、歯の動揺(揺れ)などを測定します。
歯周組織検査には、
1本の歯につき1点の歯周ポケット(歯肉溝)を測定する“歯周基本検査”
1本の歯につき4点から6点の歯周ポケット(歯肉溝)を測定する“歯周精密検査”
があります。
当院では、主に6点の歯周ポケット(歯肉溝)を計測する、“歯周精密検査”を行っています。
註)歯周ポケットと歯肉溝計測の違い
何れも歯と歯ぐきの境目にあるすき間(溝)の深さを計りますが、“歯周ポケット”とは歯周病になった状態のすき間、“歯肉溝”とは健康な歯ぐきの溝、と考えて下さい。
2.動機付け
・ 現在の歯周病の進行状況を説明
・ 歯周病とはどのような病気かを説明
・ 放置する歯がどうなっていくか
・ 放置すると全身にどんな影響を及ぼすか
などについて説明し、理解いただいた上で
・どのように治療していくか
を説明して、治療に取り組む意欲を高めることを、動機付けと言います。
3.歯磨き指導(プラークコントロール)
基本は毎日の自己管理(歯磨き)
歯周病 歯磨き正しく時間をかけた歯磨き無しでは、歯周病の治療は成り立ちません。
正しい歯磨きは、専門家による継続的な指導管理の下でのみ、可能となります。
自己流で時間をかけて磨くと、殆どの方が歯ぐきを傷つけ、逆にお口の中の環境を悪化させてしまいます。
最近『知覚過敏』に効く、と言う歯磨き粉が次々販売されるようになりました。
これは、歯磨きの重要性が認知され、一生懸命歯を磨く方が増えているものの、 自己流で磨いているため、知覚過敏の方が増えていることが原因です。
4.歯石除去(スケーリング)
ついてしまった歯石はとる必要があります
かつて、『歯石を取れば歯周病が治る』、と考えられていました。
しかし繰り返し歯石を取っても、歯周病は治らないことがわかってきました。
歯周病の原因は、現在ではバイオフィルムと呼ばれるバイ菌の塊が原因であることがわかってきました。
ただ、歯石がついていることにより、このバイオフィルムが滞りやすくなります。
バイ菌達は、歯石を足場として住みついています。
従って、足場をなくすことを目的として歯石を取ることは、重要な治療の一つです。
但し一度除去した後、再びつかないよう、自己管理と専門家による管理が必要です。
5.咬合調整(かみ合わせの調整)
歯周病を進行を加速する因子として重要なのが、歯に無理な力がかかること、即ち悪い咬み合せです。
咬み合せの悪い歯は、歯の表面やかぶせ物などを削り、食事や歯ぎしりの際に局所的に無理な力がかからないように調整します。
これを、咬合調整と呼びます。
6.再評価検査
“1.歯周組織検査” と同じ検査を行い、ここまでの治療の効果を調べます。
ごく初期の歯周病や歯肉炎では、ここまでで基本治療が終了し、後で述べる歯周安定期治療(SPT)やメインテナンスに移行する場合があります。
一部でもやや進行した歯周病の歯が存在する場合は、次のステップ(SRP)に進みます。
7.SRP(スケーリングルートプレイニング)
歯周病の歯の歯ぐきの下に隠れている根の部分には、黒っぽい歯石がたくさん付着している場合があります。
ここでは、歯ぐきの下の歯石を時間をかけて除去します。
歯周病の進行した方では、何度にも分けて歯石を取ることがあります。
8.再評価検査
再び “1.歯周組織検査” と同じ検査を行い、ここまでの治療の効果を調べます。
この時点で問題ないと判断した場合は、歯周安定期治療(SPT)やメインテナンスに移行します。
問題が残った場合は、“7.SRP”に戻るか、後で述べる歯周外科治療(手術)や内科的な歯周病治療が必要になります。

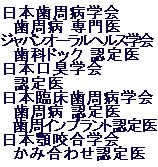

 妊婦赤ちゃんこども編
妊婦赤ちゃんこども編