(1) 歯周病の外科治療(手術)の目的
歯周病が中等度以上に進行した場合、手術(歯周外科)が必要になることがあります。
手術には様々な方法がありますが、目的は何れも
『歯周病が進行すると、どう頑張ってもご自身では清掃できない部分(深い歯周ポケットなど)が出来るので、手術はこの状態を改善し、ご自身で清掃できる形にする』
ことです。
つまり、手術をしてそれが成功したとしても、生活(歯磨き・食事等)が今まで通りであれば短期間で歯周病は再発・進行してしまいます。
また、手術を希望して来院なさる方もおられますが、他の様々な問題について事前、あるいは同時に対応しておかなければ、手術を行ってもよい結果が得られません。
歯周病は手術さえ行っておけば治る、という単純な病気ではありません。
更に、手術を希望して来院される方の多くは、かなり進行してから来院される場合が多く、すでに手遅れの場合も少なくありません。
したがって、手術の是非や必要な歯周病の手術の種類などについての詳細は、診察を受けて戴いてからでないと判断は不可能です。
歯周病手術の方法は、多岐に渡ります。
各個人の病状、体質、全身状況、生活習慣、年齢を等を考慮した上で、手術の必要性の有無、手術法の選択を行います。
なお、手術が必要な方でも、ご本人の要望により手術をしない場合もあります。
手術と聞くと、皆様は『痛い』のでは?、と二の足を踏まれるかもしれません。
しかし、さくら総合歯科の手術は、原則として痛みはありません。
麻酔も何回かに分けて、ゆっくり行いますので、殆ど痛くありません。
痛がりの方にも、安心して受けていただいております。
(2) 歯周病の手術の種類
手術は『切除療法』と『再生療法』に大別されます。
一般的に行われているのは切除療法の一種(保険診療)ですが、その方法では多くの場合再発してしまいます。
この手術は『病状安定』をめざすもので、『治癒』をめざす治療とは言えません。
治療成績の良い『治癒』をめざす手術法は、保険外診療となります。
但し、痛みや腫れは当分の間起こりませんので、患者様は安心してしまうのですが、実はひそかに歯周病が再発・進行し、気がついた時には治療不能状態になってしまいます。
当院で主に行っているのが、手術により骨の形を整えたり、歯周組織(歯ぐきや歯を支える骨)を再生する方法です。。
中等度以上の歯周病に対して行います。
『治癒』=『進行停止』を目指す治療です。
とにかく極限まで自分の歯を長く使用したい、という方に最適です。
(当院で行う手術は、通常痛くありません。)
手術は、軽症の方では必要ありません。
重症の方でも手術をしない場合がありますが、長期予後(長期間経過後の状態)に差が出ます。
再生療法は適応症が限られ、また確実性が高いとはいえませんが、その必要性の高いと判断したときに行っています。
(A) 切除療法
(a) 一般的な手術(MWF)
歯石を直接見える状態にして、歯の根を掃除する方法です。
簡単な方法ですが、治療後の組織の状態(顕微鏡で見たときの状態)が元々の状態(健康な状態)と大きく異なるので、非常に再発しやすいのが欠点です。
歯周病の手術を始めて間もない歯科医師は、まずこの方法で手術を行います。
ところが、治療成績が悪いため、若かりし頃に意欲を持って手術を行っていた歯科医師の多くは、手術後の経過が殆ど思わしくないため、やがて手術を行わなくなります。
当院でも開業当初はこの方法で手術を行っておりましたが、上記理由により現在は、行っておりません。
(b) アピカリーポジションドフラップ(APF)
正確な診断の元に行えば、確実性が高く、術後の安定度が最も良い方法です。
長期的予後が良く、当院で最もお勧めするのが、この方法です。
技術的に難しい(体に対する影響は少ない)方法で一般的ではありませんが、治療後の歯周組織の状態が本来の状態と近く、再発が起こりにくい方法です。
当院でこの手術を受けられた方の多くは、10〜20年以上経過しても大変良好な状態を維持しておられます。
(c) 遊離歯肉移植
歯磨きをしにくい環境、歯磨きで傷つきやすい歯ぐきを治す手術です。
手術法(動画)はこちら(要 WindowMediaPlayer7 以上)
(d) 結合組織移植
薄く傷つきやすい歯ぐきを厚く傷つきにくい状態にしたり、歯ぐきが痩せて歯の根が見えている場合に、その根を見えない状態にする手術です。
(B) 再生療法
(a) エムドゲイン(EMD:Enamel Matrix Derivative)
元々歯の根の表面にあるセメント質を誘導する材質で、これを手術中に歯の根の表面に塗布することにより、骨を再生させることができる可能性のある方法です。
GTRに比べて、骨の再生は少なめのことが多いようです。
メーカーの患者様用説明資料はこちらをご覧下さい。
(手術法(動画)はこちら(要 WindowMediaPlayer7 以上))
生物(ブタ)由来の材料です。
単独で使用する場合と、骨補填材(合成の骨に置きかわりやすい材料)を使用したり、下記骨移植と併用する場合もあります。
自費診療です。
(b) GTR
特殊な膜(メンブレン)と骨補填剤(骨の代わりとなる材料)を使用することにより、失った骨を再生する方法です。
適用できる症例は限られ、どの歯でも行えるというわけではありません。
骨補填剤には人体由来のもの、牛由来のもの等もありますが、当院ではより安全性を高めるという観点から、合成の物を使用しています。
(手術法(動画)はこちら (要 WindowMediaPlayer7 以上))
この方法は、特殊な膜が術後に露出するケースが多く、その結果細菌が膜を通過して感染を起こし、成功しない場合があります。
但し、術後の管理次第では、最も多く骨を再生させることが可能な方法です。非吸収性材料(2回の手術が必要)を使用する方法は成功率が比較的高く、主流となっておりましたが、平成22年末でメーカーが生産から撤退したため、現在は吸収性の材料(手術は1回)しか使えません。
吸収性の材料は、膜が露出した場合の結果が好ましくなく、今後行われる機会が少なくなって行くと思われます。
自費診療です。
GTRの保険導入について
平成20年4月より、この方法を保険で行うことが出来るようになりました。
ただし、(現在のところ)骨補填材が使用出来ません。
骨補填材を使用しないと、成功率が低くなるとの評価が多いので、注意が必要です。
また、現在認可のおりている材料が吸収性の物ばかりで、治療成績の良いといわれている非吸収性の材料が、今のところ使えません。
(ハ) 骨移植(自家骨移植・他家骨移植・人工骨移植)
歯周病によって失われた歯槽骨を、患者様ご自身から採取したり、他人の骨を移植したり、人工の骨を使って移植したりする方法のこと。
当院では、ご自身の骨を使用する自家骨移植を行う場合があります。
また、採取できる骨に制約がある場合、人工骨を併用する場合もあります。
自費診療となります。
参考1:GEM21S(Growth factor Enhanced Matrix)
GEM21S(ジェム21)とは、rh PDGF(血小板由来成長因子(Platelet Derived Growth Factor))とβ-TCP(超多孔性合成βリン酸三カルシウム)で構成された物質で、これを手術により骨がなくなった部分に詰め込むことで、骨と粘膜の両方を大幅に治すことが出来る、といわれている方法です。
米国 Osteohealth社の製品です。
ただ、現在のところ上記エムドゲインより明らかに臨床成績がよい、との報告はなく、多大な期待は禁物です。
現在日本では認可されておらず、直接海外から輸入して使用することになります。
現在世界で広く行われている方法の中では、比較的新しい方法です。
100%合成された材料です。
なお、当院では取り扱いしておりません。
参考2:骨膜移植
GTRで使われる膜の代わりに、ご自身の骨の周りにある骨膜を利用しようという考え方です。
ただ、一般的な方法ではなく、効果の検証も充分とは言えません。
(3) 歯周内科と歯周外科併用法
歯周外科を行う前に、骨の再生などの手術成績を向上させる目的で、歯周内科治療を行う方法です。
歯周病の超悪玉菌がお口の中に存在する場合に、歯周外科の結果に良い影響を及ぼします。
(4) 非外科的療法(手術をしない方法)
手術が必要な場合でも、全身的な要因(重度心臓病など)や患者様のご希望により、手術を回避する場合があります。
この場合、進行を完全に止めることはできませんが、自己管理を入念にすることにより、延命が図れます。
手術を行わず、少しでも良い結果を得たい方には歯周病の内科治療が選択枝となります。

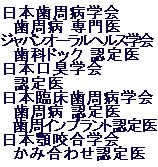

 妊婦赤ちゃんこども編
妊婦赤ちゃんこども編